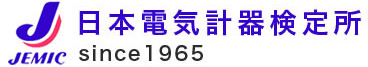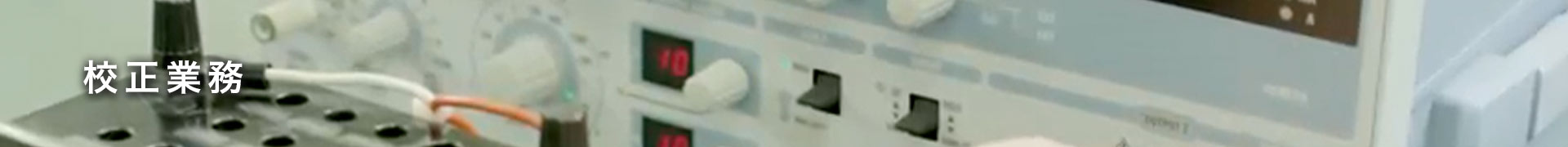
- 日本電気計器検定所TOP
- 校正業務
- 校正サービスのご案内
- テクニカルコラム
- 直動式指示電気計器について
直動式指示電気計器について
品質検査や研究開発、生産現場等様々な場面で多種多様な計測器が使用されています。近年では計測器のデジタル化が進み、通信機能等付加された便利なものが多く見受けられますが、一方でアナログ計器についても、電気設備の監視をはじめ、まだまだ多くの場所で利用されているようです。アナログ計器の特徴としては、デジタル計器と比べ構造が簡単なため応答時間が早い、価格が安い、測定量がわかりやすい、電源を必要としない等の利点があります。
アナログ計器の一つに直動式指示電気計器(以下、「指示計器」という。)があります。指示計器とは、電気量を機械的な力に変換して指針を動かし、その振れにより測定値を指示するものです。
一般的な指示計器は、駆動装置、制御装置、制動装置、指示装置、及び読取装置で構成されています。駆動装置は、入力された電気量に応じた駆動トルクを発生させ、計器可動部(指針)に回転力を生じさせるものです。制御装置は、駆動装置で発生した駆動トルクに対して、逆向きに制御トルクを発生させる装置です。両者の力が平衡するところで、指針が停止するように制御します。そして、制動装置は、速やかに可動部の変位が安定するように、可動部の運動に対して適当な制動トルクを与えるものです。駆動装置、制御装置、制動装置は、指示計器の3要素と言われており、指示計器に必要不可欠なものです。その他、指示装置には指針軸の軸受、読取装置には指針や目盛などが含まれています。
指示計器は、仕様回路や測定対象によって分類されており、主な指示計器の分類は以下の通りです。

指示計器を利用する場合、固有誤差は重要な情報です。固有誤差とは、計器及び/又は付属品の標準状態での誤差と定義されています(JIS C 1102-1:2007)。標準状態とは、姿勢や周辺環境など許容誤差を規定するために定めた影響量の値又は範囲を指します。標準状態には、指示計器の姿勢(垂直/水平)や周囲環境(外部磁界や外部電界がないこと)等が規定されています。これらは必ずしも銘板に記載されているとは限らないので、取扱説明書をよく確認して使用する必要があります。
電圧計や電流計等の指示計器の固有誤差(百分率)は、以下の式で計算されます(JIS C 1102-9:1997)。
固有誤差(%) = 目盛線 -入力値 基底値 ×100
基底値とは、誤差の基準となる規定された値で測定範囲の上限値やスパンです。例えば、上限値(基底値)が100 Vの直流電圧計の目盛線(指示値)100 Vを試験し、入力値(校正値)が100.2 Vであった場合を考えると、指示計器の固有誤差は、-0.2 % = (100-100.2)/100×100 となります。指示計器の固有誤差には限度があり、指示計器の銘盤に記載されている精度階級に対応する限度を超えてはいけないことになっています。
指示計器を精度階級どおりに維持管理するためには、適切な校正により固有誤差を確認しておくことをお勧めします。指示計器の校正をご検討の際は、是非一度、JEMICにお問合せください。
(2025.2 F)
計測器の校正業務
校正サービス
デジタル校正証明書等の発行について
デジタル校正証明書等のダウンロードについて
お見積り・お申込みの手続きと、納期・費用について